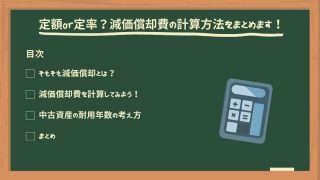 資産形成
資産形成定額or定率?減価償却費の計算方法をまとめます!
「減価償却費」という言葉に聞き馴染みはありますか?個人事業主で毎年確定申告をしている方や、所有している不動産の売却をしたもしくは検討している方はよく聞く言葉だと思います。僕も不動産投資を始め、確定申告をするときにちょこっと勉強しました。これから不動産を所有しようかと思っている方や今年から個人事業主になり、初めて確定申告をしなければならない方のために、減価償却費の算出方法についてまとめていきたいと思います。
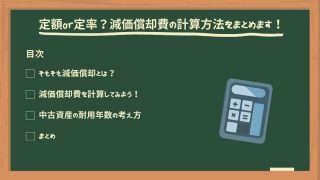 資産形成
資産形成 運用実績
運用実績 運用実績
運用実績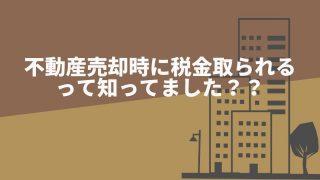 資産形成
資産形成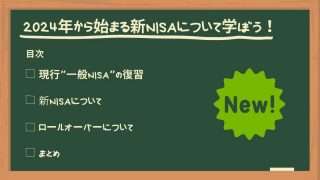 資産形成
資産形成 運用実績
運用実績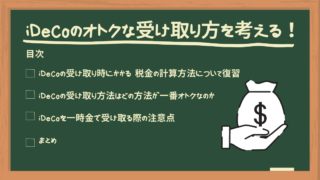 資産形成
資産形成 資産形成
資産形成 運用実績
運用実績 資産形成
資産形成